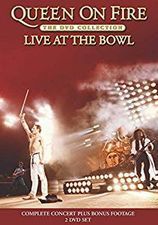2009年07月26日
ミニマル・ミュージックとは?。
今回は「ミニマル・ミュージック」(短くミニマルと呼ばれることもあます)をチョッと真面目に
調べたことを書いてみたいと思います。(長々書いてしまっています、スミマセンです!)
ところで皆さんは「ミニマル・ミュージック」をご存知でしょうか?オイラは近年、友人に教えて
もらいました。ミニマル、音の動きを最小限に抑えパターン化された音型を反復させる音楽
のことであくまで単純な反復のリズムがメインであり、曲として成り立つ最低限度に近いほど
展開も少ない。
しかしそれらの中での微細な変化を聞き取るのが目的であり、全体的な視点から見れば決して
無駄な反復ではなく、音楽は徐々に展開しているのです。たまに(オイラもそうだったですが)、
テクノと呼ばれるジャンルの電子音楽が細かな反復を伴うスタイルを多く用いる事から、テクノが
ミニマルミュージックのジャンル、または反対にミニマルミュージックがテクノのジャンルであると誤解される
場合があるようでして、実はこの両者は必ずしも一致する訳ではないありませんでした。
確かにミニマルミュージックでも電子音を伴わずに生楽器のみで演奏する音楽は数多くあるし、
テクノでも反復を伴わない音楽は多いのですから。(なるほど、でも結構微妙な感じだな)
ミニマル・ミュージックの最初のきっかけはミニマルを代表する作曲家:スティーヴ・ライヒが
テープ音楽によるパフォーマンスを試みたことに始まり、原点こそテープループという機械的技術から
生まれたものですが、実はヨーロッパおよびその他多くの地域の伝統音楽には反復の要素が多く見られ、
音楽的な発想としては昔から多くの民族において認知されている語法だと言えらしい。
ヨーロッパに話を限定すれば東欧の民俗音楽にはオスティナート(音楽的パターンを反復する技法)が
多く見られる。例えばショパンがよく用いたマズルカの様式の原点にあたるポーランドの民俗舞踊
マズール、クヤヴィヤク、オベレックは、基本的に反復オスティナートに基づいている。
またクラシックの近代音楽においては、ラヴェルの後期(ピアノ協奏曲等)、ストラヴィンスキーの作品
(初期の三大バレエおよび後年の「結婚」等)またオルフの諸作品などに見られるオスティナート語法は、
西洋音楽史において後のミニマルにつながるとも言えるでしょう。
例えばエリック・サティの後期作品は執拗な反復によって曲が成り立っており、ミニマル・ミュージック
へと続く音楽形態を脈絡と後年への音楽シーンに深く影響を与えている・・・。
というところで、難しい音楽的お話は終わりにしたいと思います。(勉強不足でスミマセンです!)
最後にオイラのお袋も聴いているミニマル・ミュージックの巨匠、スティーヴ・ライヒ(Steve Reich)の
代表アルバムと言っても過言ではないアルバム「18人の音楽家のための音楽」をUPしたいと思います。

作曲・指揮はスティーヴ・ライヒ、演奏はドイツの室内合奏団:アンサンブル・モデルンです。
まずは論より証拠です。どうぞこの不思議な感覚をご堪能下さい。
※しかし音楽とはホントに奥深くまた神秘的なものだと勉強させられました。それと現代音楽の解釈もまた
オイラの鈍い頭で解説?してみたのですが危うくショートしかけました・・・。 END
告知です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
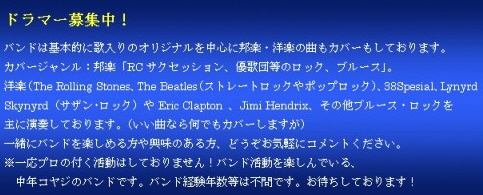
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調べたことを書いてみたいと思います。(長々書いてしまっています、スミマセンです!)
ところで皆さんは「ミニマル・ミュージック」をご存知でしょうか?オイラは近年、友人に教えて
もらいました。ミニマル、音の動きを最小限に抑えパターン化された音型を反復させる音楽
のことであくまで単純な反復のリズムがメインであり、曲として成り立つ最低限度に近いほど
展開も少ない。
しかしそれらの中での微細な変化を聞き取るのが目的であり、全体的な視点から見れば決して
無駄な反復ではなく、音楽は徐々に展開しているのです。たまに(オイラもそうだったですが)、
テクノと呼ばれるジャンルの電子音楽が細かな反復を伴うスタイルを多く用いる事から、テクノが
ミニマルミュージックのジャンル、または反対にミニマルミュージックがテクノのジャンルであると誤解される
場合があるようでして、実はこの両者は必ずしも一致する訳ではないありませんでした。
確かにミニマルミュージックでも電子音を伴わずに生楽器のみで演奏する音楽は数多くあるし、
テクノでも反復を伴わない音楽は多いのですから。(なるほど、でも結構微妙な感じだな)
ミニマル・ミュージックの最初のきっかけはミニマルを代表する作曲家:スティーヴ・ライヒが
テープ音楽によるパフォーマンスを試みたことに始まり、原点こそテープループという機械的技術から
生まれたものですが、実はヨーロッパおよびその他多くの地域の伝統音楽には反復の要素が多く見られ、
音楽的な発想としては昔から多くの民族において認知されている語法だと言えらしい。
ヨーロッパに話を限定すれば東欧の民俗音楽にはオスティナート(音楽的パターンを反復する技法)が
多く見られる。例えばショパンがよく用いたマズルカの様式の原点にあたるポーランドの民俗舞踊
マズール、クヤヴィヤク、オベレックは、基本的に反復オスティナートに基づいている。
またクラシックの近代音楽においては、ラヴェルの後期(ピアノ協奏曲等)、ストラヴィンスキーの作品
(初期の三大バレエおよび後年の「結婚」等)またオルフの諸作品などに見られるオスティナート語法は、
西洋音楽史において後のミニマルにつながるとも言えるでしょう。
例えばエリック・サティの後期作品は執拗な反復によって曲が成り立っており、ミニマル・ミュージック
へと続く音楽形態を脈絡と後年への音楽シーンに深く影響を与えている・・・。
というところで、難しい音楽的お話は終わりにしたいと思います。(勉強不足でスミマセンです!)
最後にオイラのお袋も聴いているミニマル・ミュージックの巨匠、スティーヴ・ライヒ(Steve Reich)の
代表アルバムと言っても過言ではないアルバム「18人の音楽家のための音楽」をUPしたいと思います。

作曲・指揮はスティーヴ・ライヒ、演奏はドイツの室内合奏団:アンサンブル・モデルンです。
まずは論より証拠です。どうぞこの不思議な感覚をご堪能下さい。
※しかし音楽とはホントに奥深くまた神秘的なものだと勉強させられました。それと現代音楽の解釈もまた
オイラの鈍い頭で解説?してみたのですが危うくショートしかけました・・・。 END
告知です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
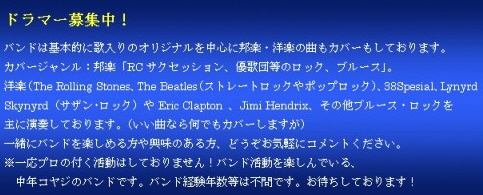
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Posted by スナフキン at 00:01│Comments(0)
│音楽